【ST通信 vol.1】ST通信、はじまりました!【STコミュニティー】
ST通信、はじまりました!
~STコミュニティーの活動から、サービスの質向上へ~
ツクイでは、「話す」「聞く」「食べる」 に関する支援を行う専門職である言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist、以下「ST」)による「STコミュニティー」を2024年度からスタートしました。
この取り組みは、ST同士がつながり、学び合い、現場での支援の質を高めていくことを目的としています。
その一環として、ST向けの情報をまとめた「ST通信」を、2か月に1回のペースでお届けします。
今回は、STコミュニティーの活動内容と、最近話題になっている「錠剤嚥下(えんげ)障害」についてご紹介します。
STコミュニティーとは?
STコミュニティーでは、以下のような活動を通じて、職種ごとの専門性を生かしながら、チーム全体のケアの質を高めることを目指しています。
- ST同士の交流・相談の場づくり
・ ST通信の発行(2か月に1回)
・ 年1回の全体研修(次回は10月17日開催予定!) - 新人STの育成サポート(年3回)
- STパンフレットの作成(STの役割をわかりやすく伝えるため)
- 口腔(こうくう)機能向上サービスの推進 など
こうした活動のひとつとして、現場での支援に役立つプログラムをまとめた冊子が完成しました。
「トレPRO-BOOK」完成!2024年度に実施したツクイの顧客満足度調査では、「余暇の過ごし方」や「機能訓練をもっと充実させてほしい」といった声が寄せられました。こうした声を受けて、全国のツクイのSTが中心となり、現場で役立つプログラムをまとめた冊子「トレPRO-BOOK」を作成しました。 | 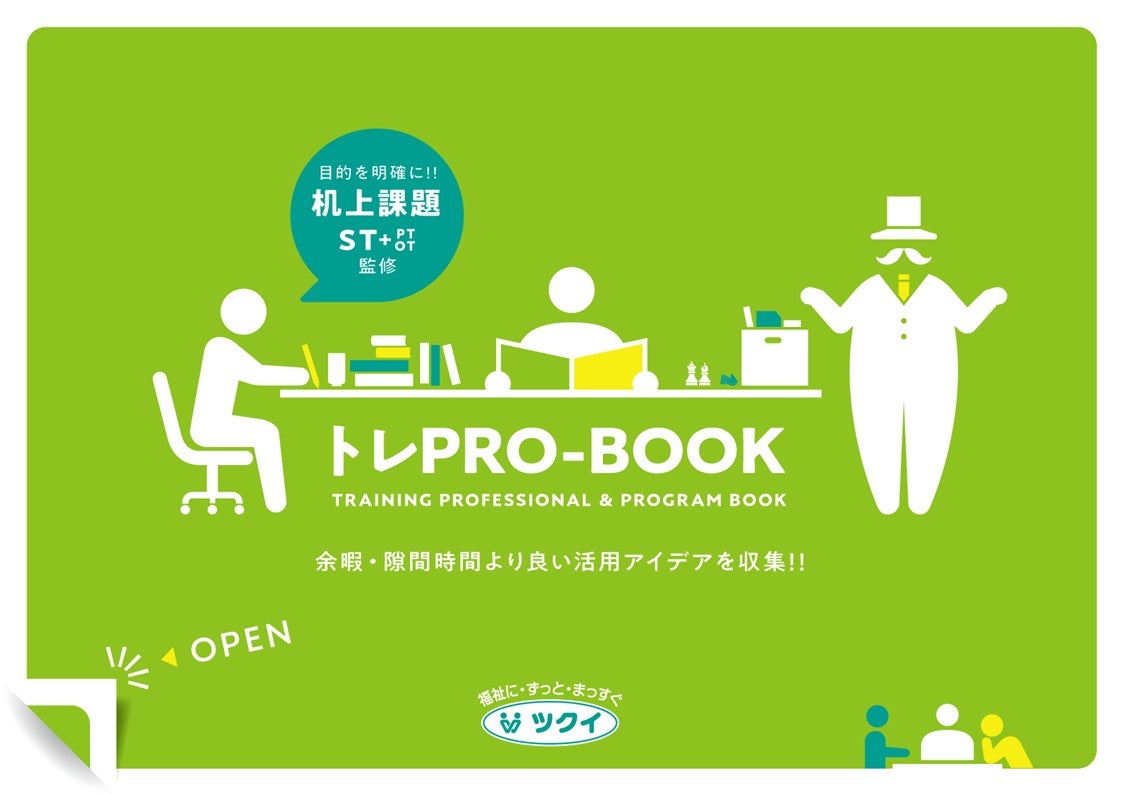 |
知っておきたい「錠剤嚥下(えんげ)障害」6月に開催された日本言語聴覚学会では、「錠剤嚥下(えんげ)障害」について報告されていました。 |  |
あらためて見直したい「頸部(けいぶ)聴診法」
STが日常的に行っている「頸部(けいぶ)聴診法」についても、基本を振り返る機会がありました。
これは、嚥下(えんげ)時の音や呼吸音を聴診器で確認し、嚥下(えんげ)機能を推定する方法です。
特に生活期では、内視鏡や造影検査が難しい場面も多く、頸部(けいぶ)聴診法が重要な役割を果たしています。
「何のために行うのか」「どんな音に注目するのか」を意識することで、より的確な支援につながります。
STの力が、ツクイのサービス品質の向上につながっています
STコミュニティーの活動は、専門職がつながり、学び合い、現場の支援力を高めるための大切な取り組みです。
こうした職種ごとのコミュニティーの活性化が、ツクイ全体のサービスの質の向上にもつながっています。
これからも、ST通信を通じて、現場で役立つ情報や取り組みをお届けしていきます。どうぞお楽しみに!
<お問い合わせ先>
サービス支援部 金谷
